こんにちは、ブログ管理人のらみらいたーです。当ブログではアフィリエイト広告を利用しています。
それでは、ゆっくりとご覧ください。
年末が近づくと、「おせちの準備、いつから始めればいいの?」「仕事や家事で忙しくて間に合わないかも…」と焦る人も多いですよね。
でも大丈夫。実は、少しの計画とコツで、誰でも余裕をもってお正月を迎えることができます。
ここでは、「おせち準備をスムーズに進める3つのポイント」から「実践ステップ」「時短テクニック」まで、忙しい人でもできる段取り術を紹介します。
おせち準備をスムーズに進めるために知っておくべき3つのポイント
理想の準備開始日はいつ?今からでも間に合うスケジュールの立て方
おせちの準備は、12月中旬〜下旬にかけて段階的に行うのが理想です。
・12月15日頃:献立を決める
・12月20日頃:買い物リスト作成・保存食材を購入
・12月28〜30日:調理・盛り付け
早めに動けば、年末のバタバタを防ぎ、家族との時間もゆっくり確保できます。
買い物リストと段取りのコツ|食材ロスを減らす計画術
おせちは品数が多くなりがち。冷蔵庫のスペースと保存期間を考えたリスト作成が重要です。
・冷凍できるもの(伊達巻・田作りなど)は先に準備
・生ものは前日に購入
・1〜2品は市販に頼ってOK
計画を立てておくことで、ムダ買いや食材ロスを防げます。
冷凍・市販・手作りのバランスを決めるコツ
「全部手作り」は理想ですが、現実的ではありません。
冷凍・市販・手作りを6:2:2くらいに分けると、味も見た目も満足できるおせちに仕上がります。
年末のバタバタを防ぐ!おせち準備の3ステップ実践法
ステップ①:2週間前から始める「計画と買い出し」
まずはスケジュールを紙に書き出すのがコツ。
「いつ・何を作るか」を見える化すれば、慌てずに行動できます。
冷凍可能な食材(黒豆、栗きんとん)はここで仕込んでOK。
ステップ②:3日前〜前日に仕込む「時短調理の工夫」
食材の下ごしらえは、一気に作らず日ごとに分けて進めるのがポイント。
煮物・焼き物・揚げ物の順で、冷蔵庫保存を活用しましょう。
ステップ③:当日の盛り付け・保存で見た目も美しく仕上げる
重箱に詰める際は、「味の濃いもの→淡いもの」「煮物→焼き物」の順に並べると彩りが映えます。
当日は保冷剤を活用して温度管理を忘れずに。
忙しくても安心!おせち準備がラクになる時短&冷凍テクニック3選
冷凍できる定番おせち食材と保存期間の目安
黒豆・田作り・栗きんとんは冷凍しても味が変わりにくく、1〜2週間保存可能。
お重に詰める前に冷蔵庫で自然解凍すれば、見た目もそのままです。
当日解凍で映える盛り付けアイデア
彩りに困ったら、冷凍の海老や市販の紅白かまぼこを使うのがおすすめ。
解凍するだけで華やかに見え、写真映えも抜群です。
プロが実践する「作り置き×冷凍」の黄金バランス
煮物類は3日前に作り、冷凍よりも冷蔵で保存すると味がなじみます。
日持ちしないものは当日に作り、冷凍で作り置いた食材と組み合わせましょう。
おせち準備の悩みを解決するQ&A
おせちはいつから作り始めるのが正解?
目安は12月28〜30日。早すぎると日持ちしにくく、遅すぎると疲れます。
29日・31日の準備でも間に合う?
29日は「苦(9)」の語呂合わせで避ける人もいますが、実際には問題なし。
31日当日でも、冷凍や市販を組み合わせれば十分間に合います。
おせちを準備しない派のスマートな年末過ごし方とは?
最近は「おせちを買って家族時間を増やす」スタイルも人気。
無理せず、心に余裕のあるお正月を迎えることが一番大切です。
まとめ|おせち準備を早めに始めて、心に余裕のあるお正月を迎えよう
おせちの準備は、「計画」「段取り」「冷凍テク」を意識すれば驚くほどスムーズになります。
完璧を目指すより、“無理なく続けられるお正月準備”を目指しましょう。
年末の慌ただしさを手放して、家族と笑顔で新年を迎える時間を増やしていきましょう。
「仕事も大掃除もあるし、今年はおせち作る余裕がない…」
そんな忙しい方にこそおすすめしたいのが、冷凍おせちの宅配サービスです。
有名料亭監修の味が、自宅で手軽に楽しめます。
下ごしらえも後片付けも不要で、時間にも心にも余裕が生まれます。


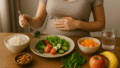
コメント